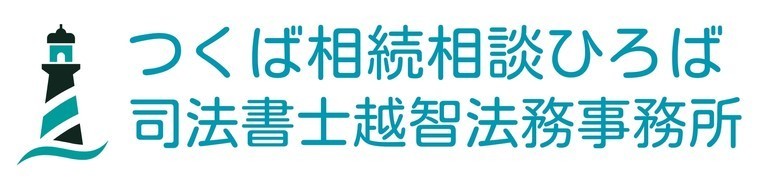運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉
相続登記義務化とは

■ 相続登記義務化の背景
2024年4月1日より、相続登記が義務化されることとなりました。この制度改革は、所有者不明土地問題や空き家対策など、喫緊の社会的課題に対応するために実施されるものです。
これまでのような任意での申請制度では、相続人の判断に委ねられていたため、様々な社会問題が発生していました。特に、公共事業の実施や災害復興において、所有者の特定が困難なケースが多発し、地域社会の発展や安全確保の妨げとなっていました。
■ 相続登記義務化の具体的内容
相続登記の義務化により、相続人は相続の事実を知った日から3年以内に登記を申請することが必要となります。ここでいう「相続の事実を知った日」とは、相続による不動産の所有権取得を認識した時点を指します。正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科せられることとなります。
注意すべき点として、この制度は2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されます。過去の相続については、施行日(2024年4月1日)または不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります。
■ 新制度「相続人申告登記制度」とは
新たに導入される「相続人申告登記制度」は、遺産分割協議が成立していない場合の対応を想定したものです。この制度では、相続人は単独で申出を行うことができ、申出をした相続人のみが義務を履行したことになります。また、相続人の一人から法定相続分による相続登記を申請することも可能です。
相続人申告登記制度の特徴として、以下の点が挙げられます
・相続人の単独申出による登記が可能
・遺産分割協議の成立を待つ必要がない
・法定相続分による暫定的な登記が認められる
■ 住所変更・氏名変更登記の義務化
2026年4月1日からは、住所変更や氏名変更の登記も義務化されます。変更があった日から2年以内の申請が必要となり、違反すると5万円以下の過料が科せられます。この制度改正は、不動産登記簿の記載内容の正確性を確保し、円滑な不動産取引や相続手続きを実現することを目的としています。
■ 相続登記放置による具体的なリスク
相続登記を放置することによるデメリットは多岐にわたります。まず、権利関係の複雑化が挙げられます。例えば、最初の相続人が登記を放置したまま死亡した場合、次の相続では相続人の数がさらに増加し、権利関係が著しく複雑化する可能性があります。
また、不動産の活用面でも「不動産売却が事実上不可能になる」「住宅ローン等の担保権設定ができない」などの問題が生じてしまいます。
さらに、相続人の中に債務者がいる場合、債権者が法定相続分による登記を代位申請し、その持分を差し押さえるリスクも存在します。また、共有持分の第三者への売却により、望まない権利関係が発生するリスクもあります。
■当事務所ができること
相続登記には様々なデメリットやリスクが伴うにもかかわらず、これまで多くの方が登記を先送りにしてきました。その背景には、相続人同士の意見調整が難しい、連絡が取れない親族がいるなど、様々な事情が存在します。
しかし、最も多いケースは、「いずれはしなければならない」と認識しながらも、手続きの複雑さや費用面での不安から、結果として長期間放置されてしまうというものです。実際に多くの方が、どこから手をつければよいのか、どのような費用が必要なのか、といった不安を抱えています。
今回の義務化により、このような状況を放置することはできなくなります。期限内の相続登記申請が求められ、違反の場合には過料が科せられる可能性があります。
当事務所では、相続登記に関する様々なご相談を承っております。少しでもご不安な点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。相続登記の専門家として、最適な解決方法をご提案させていただきます。
参照:政府広報オンライン「相続登記が義務化!所有者不明土地を解消する不動産・相続の新ルールとは?」
執筆:司法書士越智研介