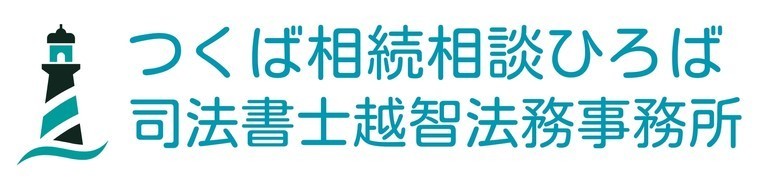運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉
相続人申告制度について

相続における不動産の手続きが大きく変わりました。令和6年4月1日から施行された「相続人申告制度」は、相続登記の申請義務化に伴い新たに設けられた制度です。これまで相続登記を先延ばしにしてきた方にとって、重要な選択肢の一つとなる制度について詳しく解説します。
相続人申告制度とは
相続人申告制度は、相続人自らが申告をすることで、相続人であることの登記がされる制度です。不動産の所有者が亡くなった際に、さまざまな事情により相続登記をすぐに申請できない場合の救済措置として設けられました。
制度創設の背景
これまで相続登記に法的な期限はありませんでしたが、「所有者不明土地」の増加が社会問題となったことから、令和6年4月から相続登記が義務化されました。全国で所有者不明土地については、九州本島に匹敵するほど多くあると言われています。
しかし、次のような事情で相続登記をすぐに申請できないケースがあります。
- 相続人間の話し合いがまとまらない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 相続人が複数名いて協議に時間がかかる
このような場合でも相続登記の申請義務化の影響を受けるため、救済措置として相続人申告制度が設けられました。
制度の特徴と重要なポイント
1. 申請期限
相続開始を知った日及び不動産の所有を知った日から3年以内が申請期限となります。これは相続登記の申請期限と同じです。
2. 他の相続人の同意は不要
他の相続人の同意なく、手続きは可能です。一人の相続人の判断で申請することができます。
3. 登記される内容
申し出をした相続人の氏名や住所等が登記されますが、他の相続人の情報や、申し出をした相続人の持分については登記されません。
4. 他の相続人への影響
重要な点として、申し出しない(登記されていない)相続人は、「相続登記の申請義務」を果たしていないことにもなります。そのため、各相続人が個別に申請するか、一人がまとめて申請する必要があります。
よくある質問とその回答
Q1: 他の相続人の分もまとめて申請できますか?
A: はい、可能です。他の相続人の戸籍や住民票(附票)等、必要書類が揃っている状況であれば、他の相続人の分も一人の方がまとめて、相続人申告登記を行うことは可能です。
Q2: 申告後に不動産を売却できますか?
A: いいえ、そのままでは売却できません。「相続人申告登記」は、所有者の相続人が誰であるかを登録するだけにすぎません。その状態では所有権は、所有者の相続人全員が共有でもっている状況、となりますので、他の相続人の同意なく勝手に他人へ贈与したり売却はできません。
売却するには、改めて相続登記を申請して新たな所有者を決める必要があります。
Q3: 数次相続が発生している場合も申請できますか?
A: はい、申請可能です。数次相続が発生していても、新たな相続人という立場であれば、申請は可能で、一次相続、二次相続、と順を追った相続人登記がなされます。
必要書類
相続人申告登記に必要な主な書類は以下の通りです:
- 申出書
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申出人が相続人であることを証明する戸籍謄本
- 申出人の住民票または戸籍附票
ただし、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)、生年月日を記載した場合は、提出を省略することができます。
注意すべき重要なポイント
1. 簡易的な手続きに過ぎない
相続人申告登記はあくまで、簡易的な登記手続きに過ぎず、権利を保全するための登記ではありません。将来的には正式な相続登記が必要になります。
2. 遺産分割協議後の期限
遺産分割協議が整い、不動産を相続する相続人(承継者)が決まったら、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければ、相続登記の申請義務を果たしたことにはならず、処罰の対象となります。
3. 放置は選択肢にならない
他の相続人と連絡がとれないから、協議がまとまらないから、面倒だから、お金がかかるから、等ということを理由に、相続登記を放置していた方も、この「相続人申告登記」という制度ができた以上、何もしないでそのまま放置は、選択肢としてあり得ないことになります。
まとめ
相続人申告制度は、相続登記の申請義務化に対する暫定的な対応策として有効な制度です。しかし、あくまでも簡易的な手続きであり、最終的には正式な相続登記が必要となることを理解しておく必要があります。
相続登記が3年以内にできる見込みがない、と思ったら、お早めに「相続人申告登記」をすすめるのがよいでしょう。手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続は誰もが経験する可能性のある重要な手続きです。新しい制度を正しく理解し、適切に対応することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
2025年7月
記事作成
司法書士越智研介