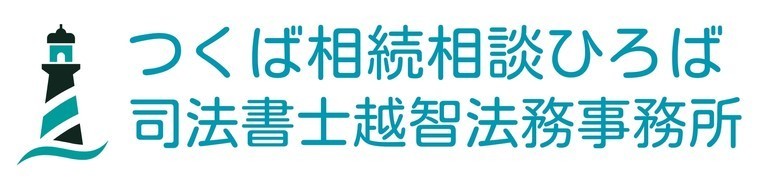運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉
どの専門家に最初に相談すればよいのか?

相続が発生した際、多くの方が「どの専門家に最初に相談すればよいのか」という疑問を抱かれます。司法書士、税理士、弁護士など、それぞれ異なる専門分野を持つため、適切な順序で相談することが、手続きを円滑に進めるカギとなります。
各専門家の役割を確認しましょう。
司法書士の専門分野
- 不動産の相続登記(名義変更手続き)
- 遺産分割協議書の作成
- 戸籍謄本等の必要書類収集
- 相続放棄の手続き
税理士の専門分野
- 相続税の申告・計算
- 相続財産の評価
- 節税対策の提案
- 準確定申告
弁護士の専門分野
- 遺産分割調停・審判
- 相続争いの解決
- 遺言書の有効性確認
- 相続人調査(複雑なケース)
相続で最初に相談する相談先として、
まずは司法書士に相談することをおすすめします。
なぜ司法書士への相談を最初に推奨するのか
1. 相続税申告が必要なケースは少ない
2023年のデータによると、相続税の申告が必要となったケースは全体のわずか10%弱でした。つまり、約90%の相続では相続税の心配は不要ということになります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、この金額を超えない限り申告義務はありません。
2. 不動産を所有する世帯は約6割
一方で、日本の世帯の約6割が持ち家を所有しているため、相続登記は必要だが相続税申告は不要というケースが圧倒的多数を占めています。
3. 法的手続きを先に整理することの重要性
戸籍謄本等の必要書類を早期に収集
遺産分割協議を適切に進行
相続登記を完了させることで、後の手続きがスムーズに
4. 相続登記の義務化によるリスク回避
2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、時間が経つほど相続人同士のトラブルリスクも高まります。
税理士への早急な相談が必要なケース
以下の場合は、司法書士と並行して、または優先的に税理士へ相談しましょう。
- 遺産総額が基礎控除額を超えている場合
- 事業承継が絡む場合
- 複雑な財産評価が必要な場合(上場株式、非上場株式、複数の不動産等)
※相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と決められており、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性がありますので注意が必要です。
弁護士への相談が必要なケース
以下のような状況では、早めに弁護士に相談することをお勧めします:
- 相続人間で意見が対立している場合
- 遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 相続人の所在が不明な場合
- 遺言書の有効性に疑問がある場合
効率的な相続手続きの進め方は?
ステップ1:現状把握
まず司法書士に相談し、以下を明確にしましょう。
相続人の確定
相続財産の概要把握
必要な手続きの全体像の把握
ステップ2:専門家の選定
司法書士との相談結果を踏まえ、必要に応じて適切な専門家を選定。
税理士(相続税申告が必要な場合)
弁護士(争いが予想される場合)
ステップ3:連携による効率的な解決
各専門家が連携することで、重複する作業を避け、効率的に手続きを進めることができます。
まとめ
相続手続きは複雑に見えますが、適切な順序で専門家に相談することで、効率的かつ確実に進めることができます。まずは司法書士に相談して全体像を把握し、必要に応じて他の専門家との連携を図ることが、最も効率的なアプローチと言えるでしょう。
突然の相続で何から始めればよいか分からない場合は、まず司法書士にご相談いただくことで、安心して手続きを進めることができます。
2025年7月
記事作成
司法書士越智研介