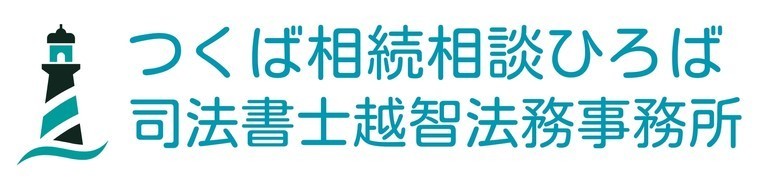運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉
相続手続きにおける「戸籍謄本」について②

今回は相続手続きに必要な戸籍について、わかりやすく整理してお伝えします。
なぜ出生から死亡まで全ての戸籍が必要なのか
相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が求められます。これは相続人を正確に特定するためです。
法定相続人の優先順位
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位:子・孫(直系卑属)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹・甥姪
上位順位の相続人が存在しない場合に、次の順位に相続権が移ります。同じ順位内でも、被相続人により近い関係の方が優先されます。
全期間の戸籍が必要な理由
現在の戸籍だけでは見えない重要な情報があるからです。例えば、離婚した前配偶者との間に生まれた子や認知した子の存在、過去の養子縁組の履歴、転籍による本籍地の変更歴などは、現在の戸籍には記載されていない可能性があります。戸籍が改製される度に、従前の重要な情報が新しい戸籍に引き継がれないことがあるため、相続人の見落としを防ぐためにも生涯にわたる戸籍の確認が不可欠となります。
戸籍の効率的な取得方法
戸籍取得において最も効率的なのは、出生から順番に追うのではなく、死亡時の戸籍から出生に向かって遡る方法です。これにより、本籍地の変遷を正確に辿ることができます。もし本籍地が不明な場合は、最後の住所地で「本籍地記載あり」の住民票除票を取得すれば、本籍地を確認することができます。
実際の取得は、該当する区役所・市役所の戸籍係に申請します。その際、「相続手続きで出生からの戸籍が必要」と伝えることで、担当者が適切な戸籍を案内してくれます。
これまでは、本籍地が変更されている場合は、それぞれの管轄役所に個別に申請する必要がありましたが、現在は「広域交付制度」により最寄りの市区町村の窓口でまとめて取得することが出来るようになりました。
※詳しくは【法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」】
申請書については各自治体で書式が異なるため、事前に役所のホームページから書式をダウンロードしておくとよいでしょう。委任状が必要な場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
取得範囲について
金融機関や法務局によって要求される範囲が異なることがあります。「成年に達する年齢まで」で十分とする機関もありますが、出生まで求められる場合も多いため、出生記載のある戸籍まで取得しておくことをお勧めします。
相続手続きはこの戸籍収集から始まることが多いため、早めに準備を進めることが大切です。
2025年9月
記事作成
司法書士越智研介